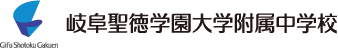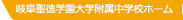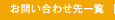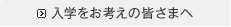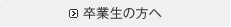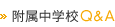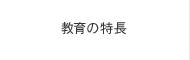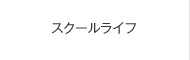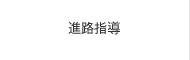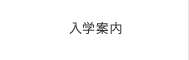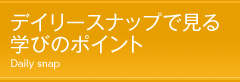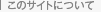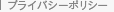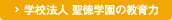報恩講がありました
本日午後に報恩講が行われました。
今回は、圓勝寺のご住職でいらっしゃる橘行信先生をお招きして、「弔う」と題したご法話を拝聴しました。
「弔う」は、もともと「訪う」と書き、亡くなられた方の人生をたどり訪ねることを指しました。そして、自分自身の人生の行き先を思い訪ねることでもあったのです。
かつてはお通夜、お葬式では、地域の方々総出で準備し行われるものでした。お通夜では、書道の紙に十二光を書き、お葬式後の出棺にて、これらの紙を棺の前後で旗として持ったのです。これは、棺に入っていらっしゃる方が仏さまに救われたことを意味します。火葬場へ向かう道では、六道を表す6本の蝋燭が立てられ、棺が通り過ぎるとその火を消し、故人が六道の迷いを通り越して仏さまに救われたことになるのです。
火葬場では、火葬を務める人が亡くなられた方を焼きました。火葬役の人は、地域で何十年も一緒に過ごしてきた親しい人を焼かなければなりません。亡くなられた方を焼くときも、お骨を納めるときも、故人のことを思いながらの葬儀。これが本来の「訪う」なのではないでしょうか。
十二光のうち、「無量光」とは、仏さまがいつでも包んでくださる光、「無辺光」とは、仏さまがどこでも私を照らしてくださる光、「無碍光」とは、仏さまがどこまでも届けてくださる光です。
現代はお通夜やお葬式は業者にお任せとなっていることが多いですが、そんな中でも亡くなられた方の人生を訪ね、そして自分のこれからの人生も訪ねることはできるはずです。